| |
授業の流れ |
| |
1.導入(標本:赤色の袋と青色の袋)
「ここに、二枚の袋があります。だれかこのわきの部分を引っ張ってみませんか?」と一人の子どもを指名し、二枚の袋を引っ張らせます。すると、青色の袋だけが破れてしまいます。その二枚の袋を実物投影機に映し出し、赤色の袋の縫い方である「返し縫い」という縫い方の名称を教えます。
次に、子どもが普段使っている袋や教師が用意した袋などの縫い目を提示しながら、『製作する物は丈夫に縫いたい』という子どもの意識を高めさせます。 |
| |
2.縫い方のポイントを考える(標本:赤色の布と黄色の布)
 |
| 標本:赤色の袋と青色の袋 |
各グループに二枚の標本を配付します。赤色の布は正しい返し縫いをしていますが、黄色の布は返し縫いをする際、針を上げたままで布の向きを変えたため、縫い目がそろっていません。「両方とも返し縫いをしていますが、仕上がりに違いがあります。違いの原因は何かを考えましょう。」と指示を出します。子どもたちは、標本を観察したり、練習布を実際に縫ってみたりしながら、二枚の標本の縫い方の違いを考え、話し合います。
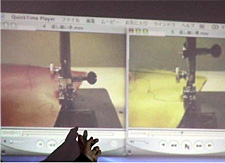 |
| 図1:二つの縫い方の比較 |
子どもたちの考えを発表させた後、「スクリーンに二つの縫い方を映します。縫い方の違いを見つけましょう。」とスクリーンに注目させます。二つの縫い方を横に並べ、最初は一つずつ再生します。二回目は、ポイントとなる場所(布の向きを変える時)で映像を停止します。(図1)すると、ほとんどの子どもは針の位置の違いに気づくことができます。 |
| |
|
|
|
| |
3.製作する
いよいよ、製作に入ります。ペアをつくり、布の向きを変える時に針を下ろすことができているかを確認させます。
製作中、スクリーンには、返し縫いの映像(デジタルコンテンツ:ポイント)を繰り返し提示しているので、ポイントを確認したい子どもはいつでもスクリーンを見ることができます。
|
|
|
| |
|
| |
4.評価する
『両端だけを二度縫いする』ということが理解できない子どももいます。そこで、評価にアニメーションのコンテンツを使います。同じ図を示した学習シート(図2)を用意します。
図だけでは分からない子どものために、(デジタルコンテンツ:評価)を提示します。何度も繰り返し再生することができるので、便利です。 |
|
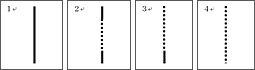 |
| 標本:赤色の袋と青色の袋 |
|
 |
|
「今日は返し縫いをします。布の向きを変える時は針を下ろしましょう。」と一方的に指導するのではなく、標本を観察させたり、映像を見比べさせたりすることによって、子どもたちの返し縫いへの関心を高めることができます。
ミシンを使うことが嫌いな子どもは少なくありません。理由は、「分からない。」「できない。」からです。本当に困っている子どもは、教師に尋ねることさえできないでいます。デジタルコンテンツを活用することによって、教師はまわりに集まる子どもへの対応に追われるのではなく、本当に支援の必要な子どもへの対応ができるようになります。
|
|
|
|